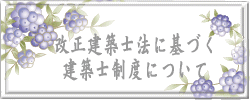 改正建築士法に基づく新しい建築士制度について 本年11月28日、新しい建築士制度がスタートします。 建築士制度が以下の点を中心に大幅に見直されますので、ご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <新たに義務づけられる事項(平成20 年11 月28 日~)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<新たに義務づけられる事項(平成21 年5 月27 日~)> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
★一定の建築物の構造設計/ 設備設計に係る法適合確認 平成21年5月27日以降は、 高度な専門能力を必要とする 一定の建築物の構造設計/設備設計に関し、 構造設計一級建築士/ 設備設計一級建築士の関与 (自ら設計する、または法適合確認を行う)が 必要になります。 ※一定の建築物とは以下の建築物のことです。 -構造設計の場合 高度な構造計算 (保有水平耐力計算、限界耐力計算等)が 義務づけられる建築物 (RC造高さ20m 超、S 造4階建て以上、 木造高さ13m 超又は軒高9m 超 等) -設備設計の場合 3階建て以上、かつ、 床面積5,000 ㎡超の建築物 ※構造設計一級建築士/設備設計一級建築士とは、 一級建築士として5年以上構造設計 /設備設計に従事した後、講習 (構造設計/設備設計や法適合確認に関する講義・修了考査)を 修了した者のことです。 ※構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が 関与していない場合は、建築確認申請書は受理されません。 但し、平成21年5月26日以前に設計が行われた 建築物の計画については、平成21年5月27日から半年間は、 経過措置として受理される予定です。 |
 |
||
 |
 |
|||
 |
 |
|||
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
★業務報酬基準の見直し等 設計・工事監理等における標準的な業務量を 定めた業務報酬基準(告示1206 号)が 見直されます。 また、工事監理業務に関し、 具体的な照合方法の詳細等について定 めたマニュアル(ガイドライン)が策定されます。 ★携帯用免許証の交付 一級建築士免許証が 携帯可能なものへと変更されます。 |
 |
||
 |
 |
|||
 |
 |
|||
 |
 |
 |
 |
 |
都道府県建築士法担当部局
都道府県建築士会(参考:http://www.kenchikushikai.or.jp/index.htm)
都道府県建築士事務所協会(参考:http://www.njr.or.jp/)
